福木まもり隊

<プロジェクト名>
備瀬区フクギ屋敷林の持続的管理に向けた剪定手法の開発
🚩活動予定
9月:沖縄県本部町備瀬区フクギ屋敷林で現地の地域住民・区長・樹木医・園芸業者・観光客を対象にヒアリング調査を行う。
11月~12月:樹木医をお呼びしてフクギの健康状態などを確認していただき、その結果とヒアリング調査から得られた情報や課題を参考に、フクギ並木の持つ多面的機能を重視した上でバランスの取れた剪定手法の策案を行う。名桜大学の有志団体「亀福会」の皆様にお力添えいただき、備瀬区及びフクギ並木の持続可能な維持・管理を推進するための募金箱を1~2カ月程度、試用期間として区内の商店に設置させてもらう。
1月:集まった募金の集計、活動中間報告のポスターを備瀬区内の掲示板にて掲載、亀福会と経過報告の共有。
2月:備瀬区公民館にて住民の方々に成果報告を行う。
🚩プロジェクト概要
私たちは備瀬区フクギ並木を数世代先の未来へ繋げていく為に、名桜大学の有志団体「亀福会」の皆様にお力添えいただき、「フクギの多面的機能を維持できるような剪定手法の考案」と「フクギ並木での募金活動」を行うことにしました。
備瀬を含む沖縄県のフクギは200年以上前に住宅を台風から守る防風林や火災を食い止める防火林として植えられました。フクギ並木が現存している備瀬区は景観の美しさから観光地として有名になっています。しかし、その一方で住民の方々の大切な生活拠点であるという面も併せ持っているのです。
道路に積もった落葉の掃除や伸びすぎたフクギの剪定、観光客が不法投棄したゴミの清掃などの景観維持に関わる作業とそれに掛かる費用の大半は高齢化の進む地域住民たちの実費で行われています。更に外部移住者の増加や元住民の高齢化が進んでいる現在、管理が困難になって過剰に剪定したり(強剪定)、台風などの自然災害、管理自体の放棄などの様々な要因から衰弱・枯死してしまったフクギも一部確認されております。
住民たちに掛かる負担を少しでも軽減し、次世代のフクギが育つまで老朽している現フクギの多面的機能維持の手助けをすることで少しでもこの地域の活性化に貢献出来たらと考えて私達は活動を続けております。
~フクギの機能~
フクギ(福木)は幹がまっすぐで、肉厚な葉を密生させる木です。そのため風の影響を和らげる効果をもち、昔から屋敷林として好んで植えられました。住宅を台風から守る防風林や火災を食い止める防火林として、人々の生活を守ってきたのです。近年では観光資源としても注目され、フクギ並木特有の青々とした木々が整然と立ち並ぶ姿や暖かな木漏れ日が、多くの観光客を魅了しています。また、備瀬区のフクギには樹齢200年以上を超えるものが多く存在します。
~地域課題~
フクギの老朽化が進む中、剪定などの管理をしっかり行うことでフクギを守っていく必要があります。しかし、住民の高齢化による管理放棄、過度な剪定(強剪定)及び都市開発のための除伐、台風による被害などによって、枯死や劣化に至るフクギは増加しています。枯死・劣化が進めば、先ほど示したフクギの機能を失うことに繋がり、環境、観光、経済、人々の生活にとって大きな損失となります。また、フクギを守りフクギに守られるという自然と共に生きる文化もなくしてしまいます。
フクギ並木のもつ多面的機能を持続させていくには、機能バランスを重視した剪定手法の開発と、よりよい方法を地域全体で共有する体制が必要です。私たちのプロジェクトでは、これらを実現していきたいと考えています。
🚩チームメンバー(★リーダー)

★三浦 巧誠(農学部・亜熱帯地域農学科 3年)
・森政 輝音(農学部・亜熱帯地域農学科 4年)
・石原 藤乃(農学部・亜熱帯地域農学科 3年)
・XIA ZEHONG(農学部・亜熱帯農学専攻 2年)


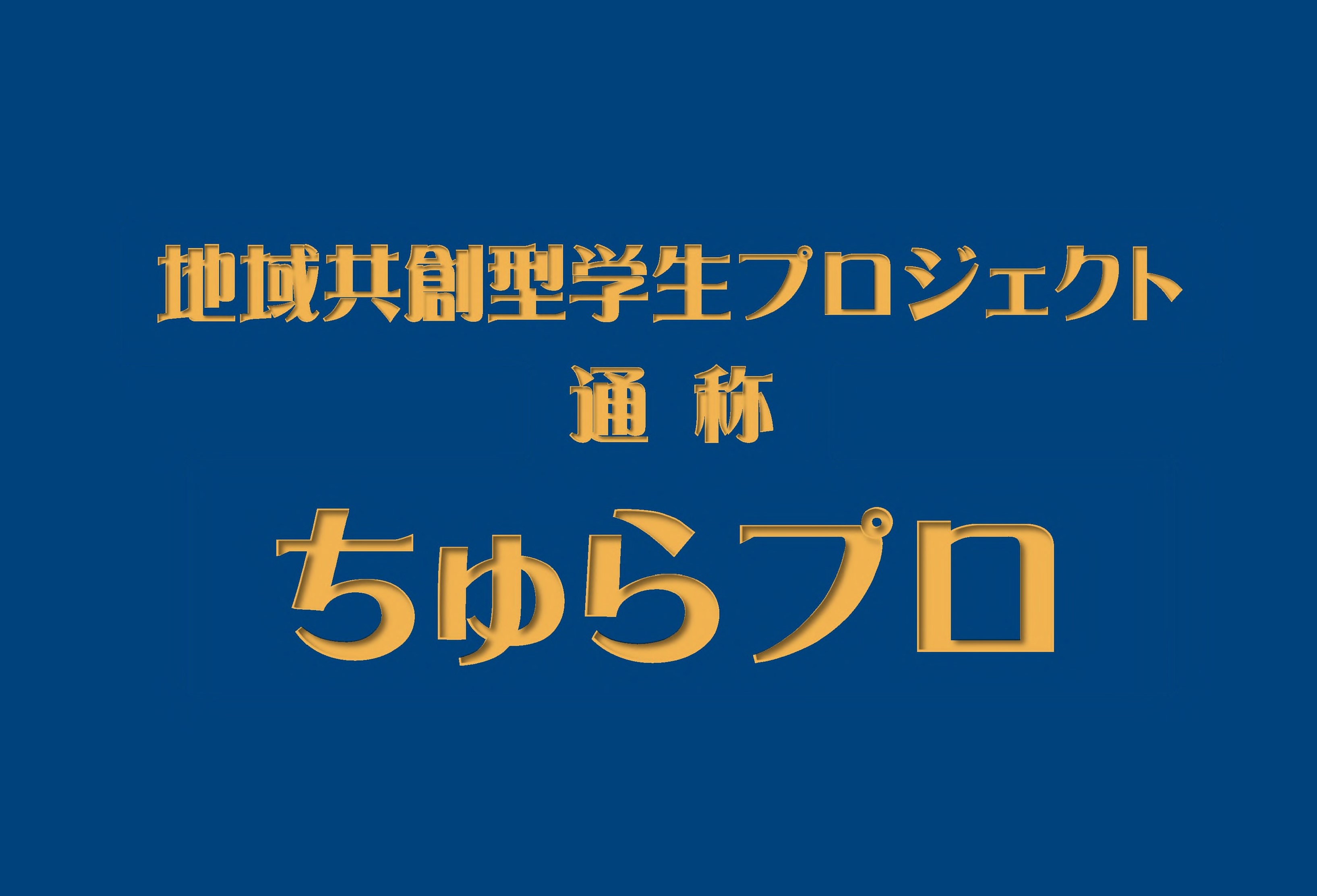
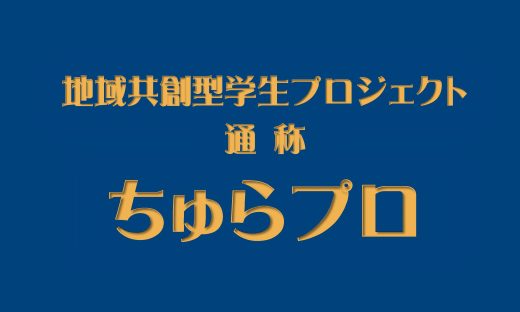
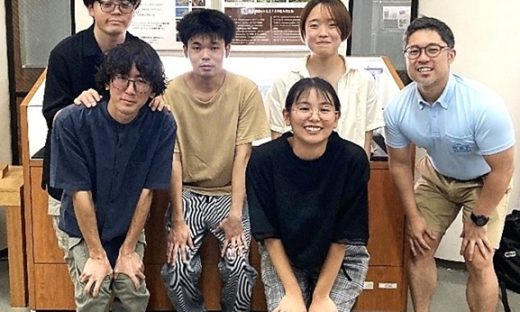

この記事へのコメントはありません。