福木まもり隊

<プロジェクト名>
備瀬区フクギ屋敷林の持続的管理に向けた剪定手法の開発
🚩活動予定
9月:沖縄県本部町備瀬区フクギ屋敷林で現地の地域住民・区長・樹木医・園芸業者・観光客を対象にヒアリング調査を行う。
10~11月:ヒアリング調査から得た情報や課題をもとに、フクギ並木の持つ多面的機能を重視した上でバランスの取れた剪定手法の策案を行う。また宜野湾市のフクギ屋敷林を対象に実施作業を行い、評価・反省を行う。
11~12月:評価・反省を繰り返し出来上がった剪定手法のマニュアル作成と沖縄県本部町備瀬区にて地域住民を対象とした成果発表会を行う。
R7年1月:フクギ屋敷林の課題に対するポスターを備瀬区地域内の掲示板にて掲示。観光客を対象としたフクギ管理ボランティアプロジェクトの設立。
🚩プロジェクト概要
私たちは沖縄県本部町備瀬区にあるフクギ並木の持続可能な剪定手法の考案、及び地域への普及活動に取り組みます。
~フクギの機能~
フクギ(福木)は幹がまっすぐで、肉厚な葉を密生させる木です。そのため風の影響を和らげる効果をもち、昔から屋敷林として好んで植えられました。住宅を台風から守る防風林や火災を食い止める防火林として、人々の生活を守ってきたのです。近年では観光資源としても注目され、フクギ並木特有の青々とした木々が整然と立ち並ぶ姿や暖かな木漏れ日が、多くの観光客を魅了しています。また、備瀬区のフクギには樹齢200年以上を超えるものが多く存在します。
~地域課題~
フクギの老朽化が進む中、剪定などの管理をしっかり行うことでフクギを守っていく必要があります。しかし、住民の高齢化による管理放棄、過度な剪定(強剪定)及び都市開発のための除伐、台風による被害などによって、枯死や劣化に至るフクギは増加しています。枯死・劣化が進めば、先ほど示したフクギの機能を失うことに繋がり、環境、観光、経済、人々の生活にとって大きな損失となります。また、フクギを守りフクギに守られるという自然と共に生きる文化もなくしてしまいます。
フクギ並木のもつ多面的機能を持続させていくには、機能バランスを重視した剪定手法の開発と、よりよい方法を地域全体で共有する体制が必要です。私たちのプロジェクトでは、これらを実現していきたいと考えています。
🚩チームメンバー(★リーダー)

★三浦 巧誠(農学部・亜熱帯地域農学科 3年)
・森政 輝音(農学部・亜熱帯地域農学科 4年)
・石原 藤乃(農学部・亜熱帯地域農学科 3年)
・XIA ZEHONG(農学部・亜熱帯農学専攻 2年)
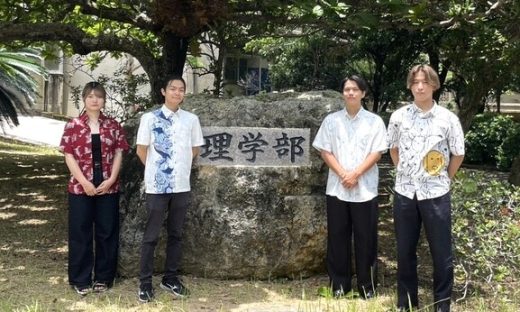


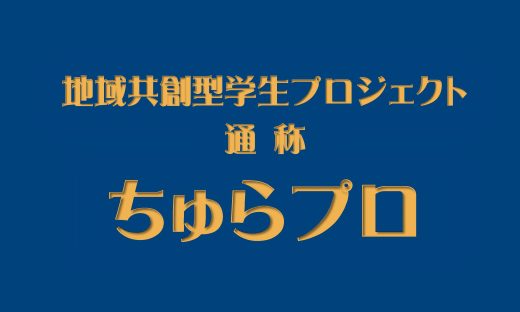


この記事へのコメントはありません。